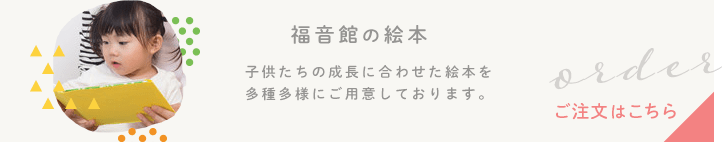30年以上に渡り園現場に寄り添い、様々な問題・テーマを取り上げ、保育の道すじを示し続ける保育雑誌「げ・ん・き」から、おススメの特集をご紹介いたします。
※本記事は、2回に分けてお届けいたします。
①:子ども時代とは何か 他 ※この記事
福岡 伸一(青山学院大学教授)

▼子ども時代とは何か
───先生は、ご講演の中などでしばしば「子ども時代」という言葉を使われています。生命としての人間にとって、子ども時代とはどういうものでしょうか?
子ども時代というのは人間にとって非常に重要な時期だと私は思っています。自分自身を振り返ってもそうですが、子ども時代に見聞きしたもの、学んだもの、気づいたものがその人の基礎となり、大人になった後もその人を支えてくれるからです。
───そもそも、大人と子どもの違いはどこにあるでしょうか。
大人と子どもの違いは、生物学的には単純明快です。
それは生殖活動ができる状態になるかどうかです。ほとんどすべての生物は幼虫とか幼生とか幼体という状態があって、成体になります。そのために必要な食べ物を食べ、エネルギーを蓄積して最短距離で直接的に大人になっています。バッタや蝶など昆虫なんかだと、卵、幼虫、さなぎ、成虫とサイクルが夏の場合だと1か月くらいです。成虫になると、生殖活動のためにパートナーを見つけて、卵を産んで次の世代へつなぐというように回っていきます。
その視点で人間という生物の成長過程を見ると、人間だけ特別な段階を経ています。とても長い子ども時代があり、しかも、ただ長いだけでなく、性的に成熟するのをわざと遅らせている猶予期間のようなものがあります。
人間に近いサルを見てみると、種類によって多少は違いますが大体5、6年で大人になってしまいます。人間はというと、長い子ども時代を経て、12、13歳くらいから思春期を迎えて、第二次性徴というのがあって、ようやく大人になります。
なぜ人間にだけそんな長い子ども時代があるのか、どうしてすぐに大人にならないのかということを、もう一度積極的に考えてみる必要があると私は思っています。生物は生きのびる上で必要な性質や生き方を選び取ってきているという進化論的な見方ができるので、私は長い子ども時代を持つことが人間を人間たらしめているんじゃないかと思っています。
───性的に成熟する前の段階が長いということはどういう意味をもちますか。
性的な行動から無縁でいられるということです。生殖活動をするようになると、生物は異性を獲得するために同性同士が競争をしなくてはならない。つまり、縄張りを持つとか、そこに入ってくるライバルを追い出すとか、生殖活動のために常に戦わなくてはいけない、守らなくてはいけない。ほとんど全てのエネルギーやリソースをそのことに割かなくてはならなくなるのです。
ところが、子ども時代には性的なことから無縁でいられるので、闘争したり、競走したり、ライバルを蹴落としたり、縄張りを守ったりすることよりもむしろ、遊んだり、じゃれたり、協力したりして、生殖活動とは関係のないこと、おもしろいこと、美しいこと、不思議なことに興味を持って探索することが許されます。
そして、この子ども時代に感じたこと、気づいたこと、知ったことというのは、後々に人間の文化を作る上でとても大事な要素として働いています。だからこそ、長い子ども時代がそのまま温存されて、人間の成長過程に組み込まれているというふうに考えたらいいんじゃないかと私は思っています。 人間をこれだけ豊かな文化を持つ生物にしているのは、長い子ども時代があるからだともいえるのです。
▼センス・オブ・ワンダー
───子ども時代に好奇心を持っていろんなものを探る、探索活動をしていく経験が、そもそも人間にとって大切ということですね。
それを私は「センス・オブ・ワンダー」と呼んでもいいと思っています。センス・オブ・ワンダーというのはレイチェル・カーソンというアメリカの女性科学者の言葉です。彼女は1960年代に環境問題に警鐘を鳴らした先駆的な科学者でした。彼女は「センス・オブ・ワンダー=神秘さや不思議さに目を見はる感性」が子どもには「生まれつきそなわっている」と言います。そして「世界中の子どもに、生涯消えることのない『センス・オブ・ワンダー』を授けてほしい」とも言っています(『センス・オブ・ワンダー』新潮社、上遠恵子訳、23頁)。

レイチェル・L.カーソン(著)
上遠 恵子(訳) 新潮社
センス・オブ・ワンダーは、大人になるとだんだんと薄れていくものですが、私は、人が成長するにつれて、性的に成熟することと引き換えに失っていってしまうものだろうと捉えています。
できることなら子どもの頃に持っていたセンス・オブ・ワンダーを持ち続けていたいし、そういうものを片鱗でも持っている大人が詩人になったり、画家になったり、また子どもにある種の気づきを与えてくれる人になると思うのです。
───保育の世界では、センス・オブ・ワンダーは大きなキーワードです。特に、非言語の世界にある子どもにとって、感性はさまざまな場面で発揮されます。
見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触れる、あらゆる五感の感性は子ども時代の方が圧倒的に優れています。子どもにしか聞こえない音もありますし、嗅覚は大人になると衰えてくることがわかっています。
子ども時代になぜ敏感な感性があるかというと、それはこの世界のあり方の美しさとか不思議さ、おもしろさに気がつくためです。その感性を十分に使って世界のあり方に気がつき、それで遊ぼうとします。その過程で様々なことを身につけますが、人間社会のルール、つまり貸し借りや契約にしてもほとんどが遊びに原型があり、遊ぶことから決まっているともいえます。
───スポーツのルールはもちろん、経済のいろんな約束というのも基本的には遊びの姿に同じものを見ることができますね。
子ども時代は、争いから無縁で遊ぶことが許される、感性を用いて、さまざまなことに触れる喜びが与えられる貴重な時期です。だからこそ、その時に何にどう出会い、何を感じるかということが大切になってきます。
▼感じるから知るへ
───子ども時代の経験が、その人の原点をつくるわけですね。
カーソンは「美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものにふれたときの感激、思いやり、憐れみ、賛嘆や愛情などのさまざまな形の感情がひとたびよびさまされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。そのようにして見つけだした知識は、しっかりと身につきます」(同、24頁)と言っています。 知るというのは言語を使って記述する、説明するということですよね。それは、科学の扉が開かれるということでもあります。知ることよりも先に、おもしろいとか、不思議だなとか、きれいだなとか、奇妙だなという気づきがある。気づきは全て感じることから出発しているので、言語の前に感じるところから始まっている、まさにセンス・オブ・ワンダーですね。

▼子どもにとって科学とは
───子どもにとっての科学、どのように捉えるべきでしょうか。
科学といっても、子どもにとっては、おもしろいものはおもしろい、きれいなものはきれい、不思議なものは不思議、というものです。
子どもの科学が始まるとは、まずは自分の感性をどう使うかということに自らが気がつくということです。とはいえ、自然やまわりの環境の中のおもしろいこと、美しいこと、不思議なことに気がつくためには、五感の使い方をある程度工夫しないと、そのメッセージに気がつくことができません。
例えば、私は虫が大好きな昆虫少年でした。虫を見つけるという時、ただ野外に出てうろうろしていれば虫が見つかるわけではありません。特別な手がかりに気がつかないといけないんです。虫は大体が隠れていますし、保護色とか擬態といった方法でカモフラージュしてできるだけ見えないようにしています。だから木にとまっているカミキリムシや蝶を見つけるためには、まるで自分がロボットになったように、特別なセンサーを装着しているように、「ビーッ」と自分の目のレンズの焦点をずらしながら、ちょうどその木の表面ぐらいに合わせてスキャンすることが必要になります。そうやって感性のレイヤーを合わせないと虫に気がつかないんです。でも一度そのレイヤーに虫がいることがわかると、次々と見つけることができます。
自分の優れた感覚に気がつき、使い方がわかることが、科学の扉が開かれる第一歩になります。そのずっと後に、どんな虫がいて、どこに住んでいて、何を食べていて、どのくらいの期間で幼虫がさなぎになり、成虫になるのかなどの知識の獲得と整理に進んでいき、言語的な説明ができるようになっていきます。
───記録する、記述する、そのための言葉と結びついていくのは、科学することがさらに深まってからということでしょうか。
科学とは、ある種、世界を言語化していくことです。自分と世界のあり方をどう結びつけていくかという、その過程すべてです。
ただ、言語化されると世界は明確になるようでいて、貧しくもなります。世界を言語化するということは、世界の干からびた骨組みだけを取り出すことでもあるのです。 それが言語の働きなので仕方がないのですが、だからこそ、非言語の時間をたっぷり過ごす子ども時代に、いろんな変なこと、無駄なこと、無駄に見えることをやれることが大事なことです。大人はそれを妨げてはいけないんですね。
▼どんなものも科学できる
───先生の場合は「虫」が興味の対象でしたが、絵を描くことに興味を持つ子どもに置き換えてもよいお話ですね。対象への気づきや感性、色や光や線への感性があり、自分なりに深めていくプロセスですね。また、運動であれば、身体とその動きとまわりの世界の関係を知っていくことでもあります。
我々大人が、理系、文系と分類して美術、技術などと科目を勝手につくっているだけですね。私からすると芸術も科学です。芸術もその世界をどう捉えるかということを考えて、絵を描く人はキャンバスの上に、彫刻をする人は石の形としてその世界を記述しているわけです。science(科学)の語源はラテン語のscientia(知識)で、scientiaはscio(知る)の派生語なので、「科学」の語源はもともと「知る」からきているのです。
私が大好きな画家フェルメールが生きた時代、17世紀は、ガリレオが望遠鏡で天体観測して、顕微鏡のもととなるものを作り出したレーウェンフックがミクロの世界に分け入っていった時代です。
彼らは方法こそ違いますが、たえまなく変わりゆく動的な世界のあり方をなんとかして捉えたい、書き留めたいと同じことを希求していたんです。科学と芸術が分離してしまう前の、実に豊かな時代に彼らは生きていました。近代になって職業化して細分化されすぎてしまい、いろいろなものが分類されてしまいましたが、この世界の美しさに気がついてそれと自分をどう距離を縮めていくか、あるいはそれをどう自分の中で表出、表現するかという行動自体が科学というふうに捉えられるのではないでしょうか。そういう意味ではすべての子どもが行なっているのは科学の原型ですし、すべての子どもは科学的な行動をとれるはずなんです。
全ての人間の芸術活動、経済活動の原型は子ども時代の遊びや気づきの中にある。自然でも人工物でもそのものの発するメッセージを受け止めて、それに対して自分がどうメッセージを送り返すのか。人間の文化的な活動全てそこに原点があると思います。
───子どもに好きなことがある時、ついそれを将来の職業などとつなげて語り、その方向性を分類してしまいます。大人の悪い習慣です。
私はたまたま虫好きが嵩じて生物学者になっていますが、必ずしも自分が好きだったものがそのまま職業になる必要はありません。好きなものはそのまま趣味になってもいいし、変わってもいいし、大切にしているままでいい。どんな形であれ、その人を支え続けていくものであることは間違いないと思うんですね。そして、その時のアプローチの仕方というのは、その後にいろんなところで役立つし、その人を励まし続けてくれます。カーソンも言っています。「地球の美しさと神秘を感じとれる人は、科学者であろうとなかろうと、人生に飽きて疲れたり、孤独にさいなまれることはけっしてないでしょう。たとえ生活のなかで苦しみや心配ごとにであったとしても、かならずや、内面的な満足感と、生きていることへの新たなよろこびへ通じる小道を見つけだすことができると信じます。」(同、30頁)
好きなもの、好きなことというのは自然物に限らず、例えば車や電車とか人工物でもいいのです。色や形や様態がメッセージを発しているので、デザイン性を持っているということはメッセージを発しているということ。そのメッセージを子どもは受け止めている。かっこいいとかおもしろいとかきれいだとかそういうことに気がつく、受け止めることはまぎれもなくセンス・オブ・ワンダーではないでしょうか。
───子どもの目線からは、自然環境には多様な気づきがあるとは思いますが、対象はそれだけではないということですね。
私の子ども時代はまだインターネットもなかったですし、携帯電話もなかったのでどちらかというと自然系にいましたけれど、私の昭和の時代でも鉄道オタクのような子はいて、一生懸命電車のデザインを調べたりしていて、それもセンス・オブ・ワンダーを発揮していたと私は思っています。 最初のきっかけがどっちの方にいくかはそれぞれの個性や出遭いのタイミングによると思いますが、自然物であれ、人工物であれ、そのものが発するメッセージを受け止めるセンスを存分に使う機会と時間があるとよいですね。
福岡 伸一 ふくおかしんいち 1959年東京生まれ。米ハーバード大学医学部フェロー、京都大学助教授などを経て青山学院大学教授。生物学者。『生物と無生物のあいだ』(サントリー学芸賞受賞)、『動的平衡』ほか、「生命とは何か」をわかりやすく解説した著作多数。他に『フェルメール 光の王国』、『ナチュラリスト―生命を愛でる人』、訳書に『ドリトル先生航海記』『ガラパゴス』などがある。