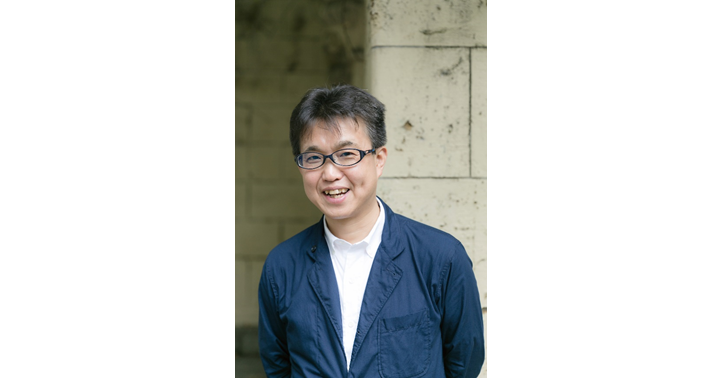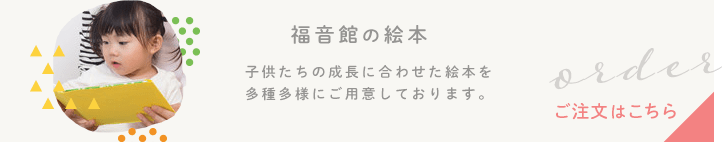遠藤 利彦
東京大学大学院教育学研究科教授
30年以上に渡り園現場に寄り添い、様々な問題・テーマを取り上げ、保育の道すじを示し続ける保育雑誌「げ・ん・き」から、おススメの特集をご紹介いたします。
乳幼児期の大切な育ちとは?
乳幼児期にどのような育ちをするかが、その後の長い人生を健康で幸せに生きられるかどうかに影響することが、様々な研究などによって明らかになってきています。
特に今、乳幼児教育の世界で関心が高いのが、「非認知」と呼ばれる領域です。これまでは、IQなどに代表されるような記憶力とか思考力とか計算力といった「認知能力」を獲得した人が、その後の人生で社会的・経済的に成功すると考えられてきました。
しかし、そうした「できる」「できない」といったことだけではないこと、つまり「非認知」なるものが、人生に大きく影響することが指摘されるようになってきました。
もちろんこれまでも、教育現場の数多くの実践者たちは、テストで測ることができる認知能力だけではない、「非認知」なるものが重要であることを直観レベルでわかっていたと思います。
しかしそれが客観的なデータで示されるようになってきたのです。
実際には、この「非認知的」なるものが何かについては、まだ具体的に示されているわけではなく、多くの教育の専門家によって定義づけられようとしています。
しかし、以前本誌でもお話させていただきましたが(№158参照)、私は、非「認知」能力、すなわち認知ではない、それ以外の能力ではなく、むしろ、非「認知的能力」、すなわち認知能力ではない、それ以外の心の性質こそが鍵になると考えています。
鍵となる心の性質
現実的に「非認知」として扱われるものとしては、自尊心、自制心、内発的動機づけ、共感性、道徳性、あるいは社会性と総称されるようなものは、少なくとも心理学の中では「能力」とは見なされてきていないものです。
人が高度な社会的生物として、人間自身がつくった社会の中で生きていかなくてはならない時、個人がいかに他者との関係性を構築・維持し、また集団の成員として安定した位置を確保し得るかということが、その人の心と体の健康、ひいては幸せにつながります。
その際に問われるのは、高ければ高いほど望ましいとされる「能力」ではなく、あくまでもその個人が「どのような性質の人なのか」ということです。
大切なのは「自己と社会性」
その大切なものは「自己と社会性」と呼べるものだと思います。
「自己」とは、具体的には、人から自分が受け入れてもらえる、愛してもらえる感覚、自分に自信が持てるということ(自尊心、自己肯定感)、さらに自分の衝動を抑えて行動をコントロールできること(自制心)、自分で決断して、一人で実行できること(自立心、自立性)と言われる心の性質です。
そして「社会性」とは、他者との関わりを持つ上で欠かせないものです。
自分の気持ちをまわりに上手く伝えられる、人の気持ちが理解できるといったことです。誰かが困っていたら、かわいそうだと感じる(共感)、助けてあげなければと思う(思いやり)ことも大切な要素です。だから誰かと助け合うことができ(協調性)、何が良くて何が悪いということをきちんと判断でき(道徳)、みんなで楽しくやっていくためのルールやきまりが理解できて守れます(規範意識)。
これらはすべて、人が生きて行く上で、いろいろな場面で求められるものです。
この自己と社会性は、生まれて間もない頃から育まれることが大切で、後になってがんばって身につけようとしても、年齢が上がれば上がるほど、難しくなっていきます。
だからこそ、乳幼児期にその育ちを支えることの重要性が問われているのです。
どうやって安心感を獲得するか
この自己と社会性が育まれるには、その根っことして、自分は無条件に人から受け入れてもらえる存在であること、あるいは自分は「助けて」と言えば助けてもらえる存在だという感覚を持つことが求められます。
そのためには、乳幼児期から繰り返し無条件的に、一貫して、親などの身近な信頼できる大人から護ってもらう体験をしていくことが必要です。
こうした体験を通して、人は信じられる存在だ、「助けて」と言えば助けてもらえるのが人なのだ、自分は「助けて」と言えば助けてもらえるだけの価値がある存在だという感覚を身につけていきます。
自分は愛してもらえる存在であるという実感は自尊心の中核であり、人を信じていいのだという実感は社会性の根幹にあたります。
こうしたことの大切さは、精力的に行われてきた「アタッチメント」研究によって多くわかっています。
「アタッチメント」とはくっつくこと、つまり怖くて不安な時に特定の信頼できる人にくっついて「もう大丈夫」という安心感に浸るということです。このことを繰り返し体験することで、自分が大丈夫だということを覚えていくのです。

子どもは不安に出会う存在
乳幼児期の子どもは小さくて弱い存在で、いつも不安や恐れにさらされています。
未熟な状態のまま生まれてくる赤ちゃんは、放って置かれるだけでたちまち体温が低下して生きていくことができません。
少しの間母親が離れるだけで泣き出し、一人になることだけでも大きな不安を感じます。
その他、大きな音、暗がりなど刺激に容易に反応しますし、お腹がすくことも不安の一つとして泣き出します。
身近な大人がその都度応えてケアする(くっつく)ことで、安心の状態に戻るのです。
しかしすぐにまた不安に出会い、また助けが必要になります。
もう少し成長して歩けるようになった頃でも、簡単に転ぶなどすぐに痛い目にあいます。
そんな時も、近くの信頼できる大人に感情を立て直してもらうことを求めます。
大きくなっていっても基本は同じで、遊びや運動に挑戦して失敗して不安になる、友達と喧嘩して不安になるなど、挫折を体験する度に、気持ちを受けとめて「大丈夫だよ」となぐさめてもらって、気持ちが整います。
不安に陥るたびに他者にくっついて安心するということを、人は生まれてからずっと続けて、気持ちの立て直し方を学ぶのです。
安全の基盤を形成する
私たち大人が、毎日当たり前のように生活しているこの世界ですが、まだ小さくて弱い存在である子どもにとっては、不安や恐れに直面し続ける世界です。
その度に安心を与えてくれる存在にくっつき、心と身体を整えて世界に向かっていくのです。
一日に何回と繰り返される日常を、自然に安定して経験できることで、人を信頼し、自分が人から愛してもらえるという感覚を得るのです。
逆を言えば、この安心があるから、遊びに向かい夢中になり、人に向かい気持ちよく接しようとするのです。
いわば「安全の基盤」を心の中に形成することが「自己と社会性」の大元になるのです。

基盤形成を剥奪された子どもたち
では、この大切な「安全の基盤」が心の中に形成されないとどうなるのでしょうか?
これについては、ルーマニアの施設で育った子どもたちを長期にわたって調査した研究があります。
その子どもたちは、政府運営の施設で、衛生条件が整うなか、温かい毛布で眠り、栄養もしっかり与えられていました。
おもちゃや絵本もある程度あり、生命の維持という意味では、日々の欲求を十分に満たしてもらえる環境下にありました。
しかし、そこで育つ子どもたちは心も身体も著しく発達が遅れていたり、歪んでいたりしました。
普通に食べて飲んで眠れていれば、少なくとも体の発達は保障されると思ってしまいますが、それだけでは、人は育っていかないということがわかったのです。
これらの施設で育つ子どもに欠けていたものは、人によるケアが足りないということ、つまりアタッチメントでした。
無視された子どもそれぞれの欲求
最も条件の悪い施設だと、約20人の乳児に対してケアする大人は1人しかいないという状態でした。
少ない大人で対応するので、全てが一斉になってしまいます。
ご飯を食べる時も、お風呂も、排泄も子どもの欲求とは関係なく一斉にせざるを得ませんでした。最も極端だったのは排泄です。
一列に並べられたオマルに子どもたちは一斉に座らされ、同じタイミングで排泄を強要されるという不自然なことが行われていました。
個別の子どもの欲求というのはことごとく無視されてしまうわけです。
そんな状況では、子どもが不安になった時、くっつこうとする大人がそばにいるわけがありません。
そうした状況が、子どもたちの深刻な発達の遅れ、歪みの主たる原因の一つになったことが調査研究によって明らかになったのです。
長く残ったダメージ
この研究では、原因を探るだけではなく、さらにどうしたらこの子どもたちを救うことができるかを確かめることも対象にされました。
劣悪な施設環境から里親に移った子どものその後の成長を調査したのです。
里親に移された子どもは関わりの環境が一気に好転し、身体的な健康や成長が短期間で伸び、発達的に改善される面が見られました。
また言語の面でも普通に言葉が交わされる環境に身を置くと、子どもたちは早い段階からおしゃべりが始まるということが確認されました。
しかし、そうやって環境は好転しても、ダメージが長く残ってしまう部分がありました。それが「自己と社会性」にあたる部分だといえます。
「助けて」に応えてもらえない状況
言葉を話す前の赤ちゃんがギャーと泣くということは、大人がまわりに「助けて!」と訴えているのと同じです。
何度訴えても誰も応えてくれない、助けてくれない、そういう状況がずっと繰り返されると、大人であっても人を信用しなくなってしまいます。
自分は人から助けてもらえるだけの価値がない、愛してもらえないという感覚を固めてしまうのです。
もちろん、その後も長い時間をかけていけばアタッチメントの形成を取り戻せる面もあります。
しかしそれは容易なことではなく、時間と労力がかかってしまいます。
乳幼児期に失われた経験を、後に取り戻すことはとても困難なことなのです。
貧しい信頼関係の中で育った子どもは、他者に対する不信感、自分は愛してもらえないという思い込みを強く持ってしまっているので、結果的には新しい人との関係性というのもなかなかうまくいかないということが繰り返されてしまいます。
虐待のダメージが残る理由
被虐待児について、同様のことが言えます。
虐待を受けている子どもは、泣いても放って置かれたり、むしろそれを嫌がられ、叩かれ、蹴られたりして、不安や恐れを抱いても助けてもらい安心感を得る経験が著しく少ない育ちをしています。
こうした子どもたちの中には、たとえその被虐待の環境下から離れ、適切な養育環境にうつったとしても他者と適切な関係性を結ぶことができず、社会に適応できずに苦しむケースが多くあります。
虐待を受けている子どもは、人が示すいろいろな表情の中で、怒りの表情だけにすごく敏感になるということが知られています。
一方、人が示している苦痛とか悲しみの表情には鈍感だったり、特定の表情が浮かんでいない真顔を怒っていると誤って認識したりしやすいことがわかっています。
悪意のないところにも悪意を読み取ってしまう傾向があるので、実際は優しい人からも悪意を読み取ってしまい、その人との関係がうまく築けないということが繰り返されるのです。
虐待というと、暴力をふるわれたことの痛みやつらい体験が心の傷、トラウマという形になって子どもを苦しめることを想像すると思います。
しかし、そのことよりも、痛めつけられた時に生じた恐れとか辛いという感情を、誰からも癒してもらえなかったことの方が、実ははるかに大きなダメージを長く残してしまうのです。
愛する、愛されるは一人ひとり違う
根拠なく人を信じられる人がいれば、そうでない人もいます。
この信頼関係の大元は言葉を獲得する以前の乳児期にあります。
生まれて間もない頃からと言ってもいいかもしれません。
「愛するとはこういうこと」「愛されるとはこういうこと」というのは、誰もがもっている感覚だと思います。
しかし、これらの感覚は実は一人ひとり中身が違うといわれていて、生後12ヶ月の段階からすでにはっきりとした個人差が認められています。
そして、その違いは、生まれてから身近にいる大人とどう関わってきたかによって生じるのです。
どう愛されてきたかが、どう人を愛するかになるのです。
人は大人になってから、3歳以前の具体的なエピソードを思い出そうとしても、なかなか思い出すことができません。
お母さんにこんなに優しく抱っこしてもらったとか、あの先生は自分が泣いている時に側に来て慰めてくれてすごくうれしかったという具体的なエピソードは残念ながら思い出せません。
脳のどこかには残っているかもしれませんが、取り出すことができないのです。
それは、大人になると人は記憶を言葉に置き換えるからです。
言葉を獲得する以前の記憶にはなかなかアクセスできない、そして、「わたし」を認識し始める前では自分を中心に物語を作れないのです。
だから、言葉を獲得する3歳以前の記憶がほとんどないと言われているのです。

言語以前の記憶は「期待」として残る
では、その頃の記憶が残っていないからその体験は覚えていないのかというと、そうではありません。
具体的なエピソードとして残っていないだけで、その当時の体験の記憶というのは「期待」に残ると言われています。
人が何かしてくれるという期待、自分は人から何かしてもらえるという期待です。
言葉を理解し始める前の乳児期には、人との関わりの中での1回1回のエピソードの蓄積が「期待」というところに確実に残るのです。
人生のベースとなる人を信じる感覚、自分は人から受け入れてもらえるという感覚は乳児期の段階で作られています。
信頼というのは、言ってみれば不安になって、怖くなって泣いた時にどう応じてもらえるかの積み重ねでできてくるものなのです。
私たち大人が子どもに対して行なっていること、子どもが泣いたらあやしたり、お腹がすいたらご飯を食べさせてあげたり、転んで泣いたら抱きしめてあげたり、不安で眠れない時に添い寝してあげたり、こうした何気ない当たり前の関わりが、子どもたちの将来の他者への「期待」となって蓄積していきます。
人生の幸せを左右する自己と社会性は、周囲の大人たちによってつくられてしまうといっても過言ではないのです。
すべてに応えることはできるのか
乳幼児期の子どもへの大人の関わりが、いかに大切なことであるかがよくわかったと思います。
一方で、そこまで敏感に適切な関わりができるだろうか、子どもが不安に直面した時に発せられるシグナルを察知して応えないと、子どもは不信感を固めて育ってしまうのではないかと心配になってしまうかもしれません。
しかし、このようなこともわかっています。
子どもが健全に育っている関係であっても、周りの大人は子どものシグナルに対して5割程度しかきちんと反応してないということです。
つまり、うまくできて半分、ということです。そして、こうしたことを子どもも織り込み済みのようで、自分の気持ちが伝わらないと、強く泣いたり、伝え方を変えたりするそうです。
そして、そうやって気づかれずに放って置かれたとしても、最後に自分の欲求に応えてもらえると、それまでのきちんと応えてもらえなかったという失敗は割り引いて、帳消しにしてくれるというのです。
「終わりよければ〜」ではありませんが、ちゃんと安心の場所に行き着くことができれば、それまでの苦労はナシにしてくれるわけです。
「修復」のプロセスがむしろ大事
むしろ最近では、関わりにおける行き違いや失敗の後の「修復」の関わりこそが、子どもの育ちにとって重要ではないかということさえ言われています。
最初から、いつでも、どこでも完璧な対応でなくても、失敗の関わりがあるほうが子どもにとってはいいというのです。
子どもの立場では、シグナルの出し方、救われ方につながる自己主張や表現の力を磨く機会になります。
親の立場では、子どもに対する関わり方を学ぶ機会になります。
最初からうまくいくことよりも、適度に失敗があり、最後に子どもと向き合えることが大事ということです。
虐待の子どもたちの何が救われないかというと、シグナルが気づかれないまま、不安の状態のまま、暴力をふるわれたまま、誰にも救われないままにされてしまうことです。
そこが通常の親子関係における行き過ぎたしつけ、喧嘩などと違うところです。
親子関係で時々イライラして手が出てしまったというレベルのものは、そんなに大きな影響は出ません。
もちろん、手が出てしまうことを肯定するわけではないですが、お父さんやお母さんも人間ですから、時には感情的になってしまいます。
しかし、多くの親はそんな時、やりすぎたと思った時には、「ああ、やってしまった」と反省して「ごめんね」と謝ったり、抱っこしたり、なでたりします。
また、周りの大人もフォローして、子どもの感情の立て直しを助けます。
こうした関わりがあることとないことが、虐待とそうでない関わりの違いだといえます。
人の社会性の本質
子どもは生まれてきた時に、必ず近くに自分のことをケアしてくれる人がいるという前提で生まれてきます。
人間の子どもは未熟な状態で生まれてくるので、絶対に一人では生きのびていけません。
人間は四足歩行から二足歩行になった段階で骨盤の構造が変わり、産道が狭くなりました。
本来なら21ヶ月の間、母親のお腹の中にいて生育するはずのところ、その半分以下で生まれてこなくてはならなくなったのです。
生まれても胎児期が続いている状態で、当然誰かからケアされないと死んでしまいます。
だから、そばにいる人が自分をケアしてくれる、刺激を与えてくれるという期待の中で子どもは生きていきます。
人の社会性の根っこは、人間の子どもがあまりにも手がかかるということに行き着くのではないでしょうか。
みんなが手助けしなければ到底子どもは生存、成長できなかったという進化のプロセスがあるのです。
母親だけでなく、父親、家族、あるいは、血縁関係のない人たちが集団で子育てをしていたというのがヒトの子育ての形態でした。
だからこそ、人との関係、社会性というのを強めていく要因の一つとなったとも言えます。
生物学的に見ると、進化のプロセスの中で人間自体が幼児化してきたといわれています。
人間は単体でみると鋭い牙や爪があるわけでもなく、戦う能力が弱くて、足が早いわけでもないので、逃げる力もありません。
普通だったら強くなるという進化をしていけばいいのですが、人間は真逆に進化してきたという説があります。
幼児化というと体の観点では不利なのですが、心という観点では有利なところがあります。
それは、無邪気にじゃれ合える、いつの間にか仲良くなれてしまうということです。
人間は一人だと弱いのですが、群れると俄然強くなります。
群れるためには、子どもっぽい心がとても優位に働きます。
人間はそういう性質を強めてきたことで種の繁栄をもたらしたといえます。
社会性はこれから先も人間にとって基本的なものとしてずっとあり続けると思います。
人にとって最も幸福感を感じられるのは、人との関係の中だと言われています。
「社会性」という心の性質は揺るぎないものです。
だからこそ、小さい頃にその社会性を身につける育ちを保障することは、絶対的に重要なのです。
※写真 ホリバトシタカ
遠藤利彦(えんどう・としひこ)
1962年山形県生まれ。東京大学大学院教育学研究科教授。専門は発達心理学、感情心理学。発達保育実践政策学センター副センター長。著者に『「情の理」論 情動の合理性をめぐる心理学的考究』、『本当のかしこさとは何か−感情知性(EI)を育む心理学』(編著)、『乳幼児のこころ−子育ち・子育ての発達心理学』(共著)、『赤ちゃんの発達とアタッチメント』など多数。